コラム
健康とグローバリズム
今回は、健康をキーにしたコンセプト開発に当たって、消費者が自分の身体感覚をどのようにグローバルな意識にまで拡大しているかを考えてみます。
健康を考える時の最小単位は普通、「個体(個人)」です。
ある個体が精神的にも身体的にも「恒常性」が保たれている状態を「その人は健康である」といいます。
この基本単位は、個体を構成する組織に分解され、その組織は細胞にまで分解されます。
(それ以下の分子レベル、DNAやアミノ酸まで細分化することもできますが、今回は細胞までにします)
個体を細分化する方向の健康とは逆に個体の健康を拡大する方向に進む健康意識が考えられます。
個人の健康意識が体外に「浸み出て」行って、家族、地域社会、地球にまで広がるものです。
個人の身体内環境が、生活環境、社会環境、地球環境にまで拡大したともいえます。
1990年代以降、このグローバルな健康意識が少しずつ浸透してきています。
「地球全体が健康でなければ、自分も健康とは言えない」という考えですが、これを原理的にとらえ過ぎると過激になり、他人に対して攻撃的になることもあります。
本来、健康は個人の問題ですから他人にとやかく言う(言われる)ことはないのです。
確かにそうなのですが、個人の健康もグローバルな環境から大きく影響を受けるということも事実です。
この認識は20世紀後半の10年からの強く、深くなってきています。
大きくは地球温暖化から、豆腐の原料の大豆は100%輸入されている事実から、個人の健康も地球規模の影響下にあることを消費者は日常的に感じさせられています。
嫌煙も「お節介」と「副流煙など環境問題」の両面から、より過激になっていったと考えられます。
新製品のコンセプトとして「健康」をキーワードにする場合、消費者の身体的健康意識とグローバルな健康意識との関係性を視野に入れる必要があります。
具体的には、
・生物学的な細部から発想すること → 機能に分解される自己
・心理学的、社会学的なマクロの視野をもつ → 統合され新しくなる自己
という2つの方向性でチェックする必要があります。
アミノ酸は、体のどの部分にどのようによいのか(作用機序)を訴求するだけでもコンセプトになり得ます。
それだけでなく、アミノ酸を摂取することが、新しい自己イメージを作るという方向までコンセプトで表現・伝達が可能になれば、強いコンセプトになります。
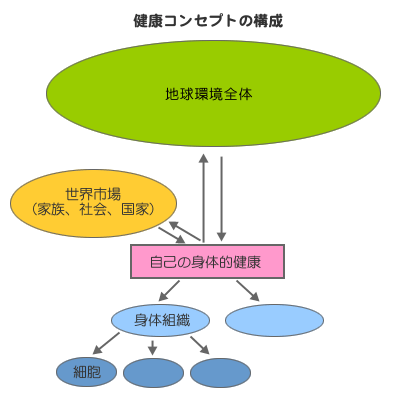
グループインタビューのモデレーションをやっていて、ここ3、4年の消費者意識の変化として、「地球環境意識」の受容性が高くなったことを感じます。
具体的には、「あなたは、○○円高くても、(地球)環境への負荷の少ないと言われているA製品を選びますか?」という質問に(実際の行動を予感させる)イエスという回答が増えていると実感します。
仮説のひとつとして、上の図式の心理過程が浸透してきたことをあげたいと思います。
天の声(マスメディアの言説)としての地球環境意識だけでなく、自己の健康意識が浸みだして地球規模にまで拡がり、そこからの逆照射としての地球環境意識という循環が成立しつつあるように思います。
もちろん、これは感触にすぎません。
このテーマを定量的に時系列で追いかけるとおもしろいのですが。
2003,4

